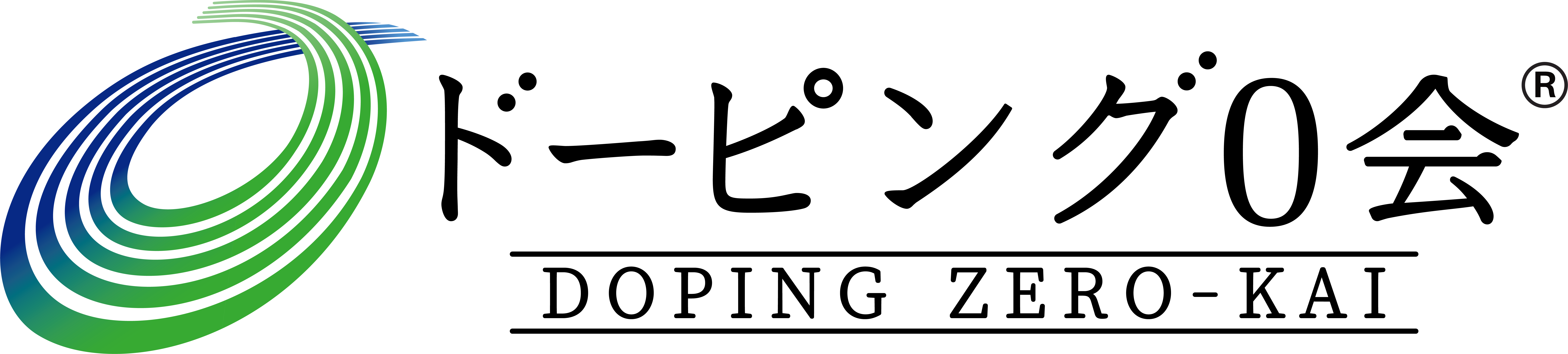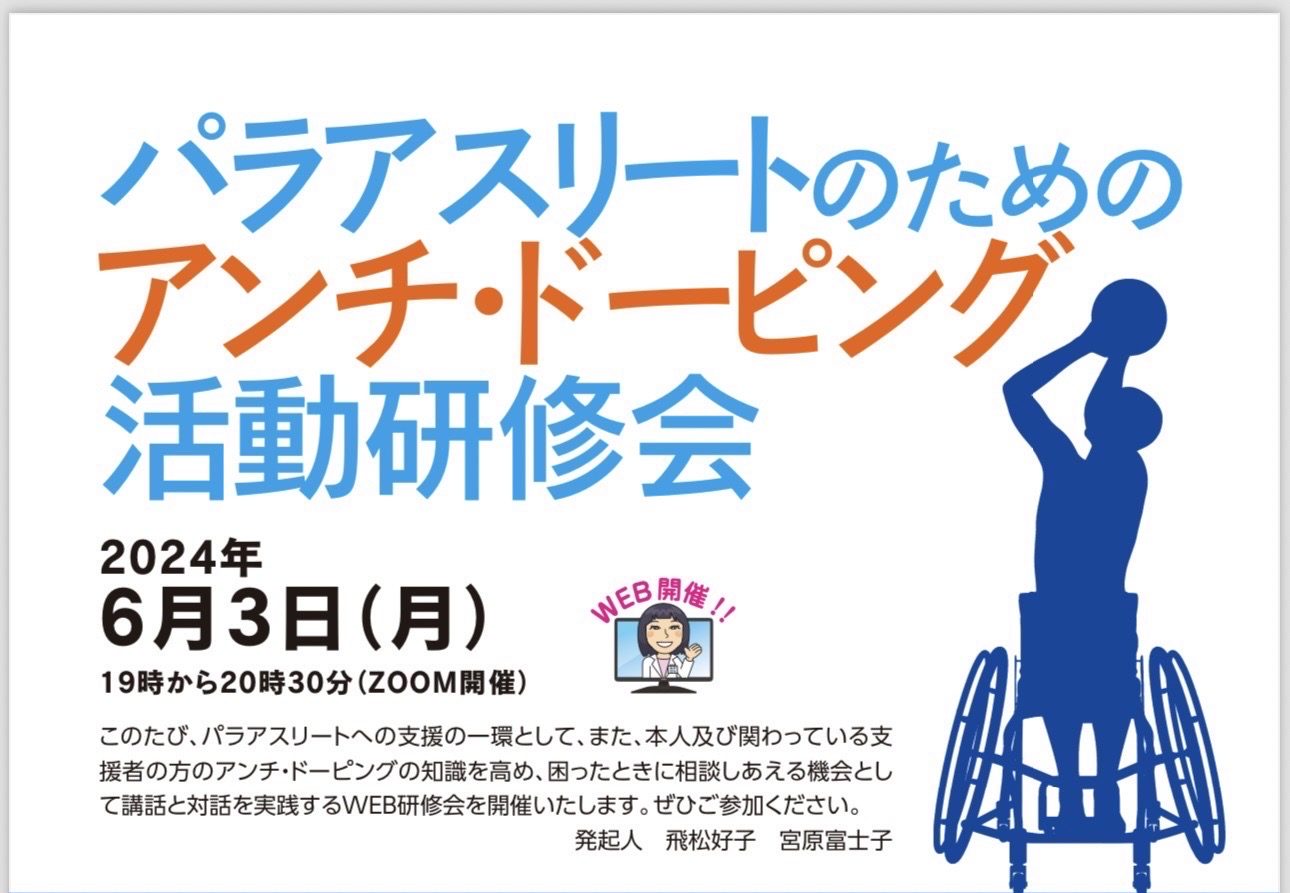みなさん、こんにちは。
一般社団法人ドーピング0会・代表理事の吉田哲朗です。
2024年6月3日(月)「パラアスリートのためのアンチ・ドーピング活動研修会」を開催いたしました。
この研修会は、特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects for Women(通称:HAP)様との連携で実施され、Zoomを用いたオンライン形式で行いました。
なぜ今「パラアスリート×アンチ・ドーピング」なのか?
これまでドーピング0会では、トップアスリートや学生アスリートを中心に、アンチ・ドーピングの啓発活動を続けてきましたが、今回のテーマは 「パラアスリート」。
実はパラアスリートの皆さんには、障がいのある身体でスポーツに挑戦するからこそ、薬や治療との距離が近いという現実があります。
そのため、ドーピングリスクや「TUE(治療使用特例)」の理解が、より繊細かつ具体的に求められる領域でもあるのです。
パラアスリートの薬の相談から始まった気づき
私がパラアスリートのアンチ・ドーピングに関心を強く抱いたのは、ある日、パラアスリートの競技者の方からいただいた質問がきっかけでした。
「てんかんの治療でずっと飲んでいる薬があるのですが、大丈夫でしょうか?」
この言葉に、私はハッとしました。
“自分の身体に必要な薬”が、“競技に出るための障壁になるかもしれない”——その不安と葛藤を、ずっと抱えてきたのだと思います。
そして私が調べて「大丈夫ですよ」と答えたとき、その方はこう言ってくださいました。
「誰にも聞けなかったので不安でしたが、これで競技に集中できます。」
この一言で、薬剤師としての私の知識が、“アスリートの不安を軽くできる”ことを強く実感しました。
当日のプログラムについて
今回の研修会では、2つのメインセッションと事例討議を通して、パラアスリートにとってのアンチ・ドーピングの現実と、支援者ができることについて深めました。
【セッション①】
「別府大分毎日マラソンの救護について」
講師:岡崎優衣 氏(一般社団法人ドーピング0会)
岡崎さんからは、パラアスリートの参加も多い市民マラソン大会における救護体制のリアルを共有していただきました。現場での対応や準備の重要性、医療従事者としての心構えなど、実践的な学びがたくさんありました。
【セッション②】
「パラアスリートのためにスポーツファーマシストができること」
講師:吉田哲朗(一般社団法人ドーピング0会)
私からは、スポーツファーマシストとして関わってきたパラアスリート支援の実例や、TUE(治療使用特例)に関する知識の普及の必要性についてお話ししました。
中でも、「あなたはドーピングができていいね」と言われたパラアーチェリー選手のエピソードは、参加者にも大きなインパクトを与えたように思います。
申請して、認可され、ルールの範囲内で正当に薬を使用しているにも関わらず、誤った認識で心無い言葉をかけられてしまう——。
だからこそ、社会全体の理解と啓発が必要だと、改めて感じました。
パラアスリートのために、できることから始めよう
今回の研修会は、「自分に何ができるか?」という問いを一人ひとりが持つきっかけになればと願って企画しました。
障がいの有無に関わらず、すべてのアスリートが安心してフェアに競技できる環境をつくるために、私たち医療者・支援者の役割は非常に大きいと感じます。
● 必要な薬を安心して使うためのTUE(治療使用特例)の制度理解
● サプリメント使用時のリスクマネジメント
● 第三者認証マークの確認やGlobal DROなどツールの活用
● 支援者が「知っている」だけで、アスリートの選択肢が広がること
「知っておくこと」「伝えられること」——これらが、アスリートを守る小さな一歩になります。
今後に向けて
今回のような、“パラアスリート”に焦点を当てたアンチ・ドーピングの場は、全国的にもまだまだ数が限られています。
しかし、今後さらに障がい者スポーツが広がっていく中で、この領域での継続的な学びと対話が必要不可欠だと確信しました。
私たちドーピング0会では、今後も多職種で連携しながら、スポーツを安心・安全に楽しめる社会の実現を目指してまいります。
ご参加いただいた皆さま、ご協力くださったHAPの皆さま、本当にありがとうございました。